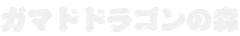- 今の仕事のままでいいのか、将来に漠然とした不安がある
- 会社に不満はあるが、いざ転職となると足がすくむ
- そもそも自分に市場価値が有るのか分からない
この記事は、こうした悩みを持つ方向けの記事です。
こんにちは、ガマドドラゴン(@GamadoDragon)です。
会社に勤めて何年か経験すると、
- 会社や、業界の問題点が見えてきたり
- 優秀な先輩や、同期が辞めていったり
- 友達とキャリアについて話したり
する機会が増えて、転職を意識するようになると思います。
しかし転職をするといっても今の会社より待遇が下がるんじゃないか、といった恐怖や、平日の多忙さから、なかなか転職活動に踏み切れる人も少ないと思います。
そんな方向けに、まずは転職のノウハウではなく、転職のために日頃から意識しておくことを学べる、転職の思考法 がオススな理由を解説していきます。
オススメポイント

上述しましたが、転職の思考法は転職の技術的な面ではなく、転職のための心構えについて記載しています。
この心構えですが、転職するつもりがない人でも知っておくだけで、その後のキャリアに大きく影響すると思います。
転職の思考法で身につく思考法は、一見当たり前のような事ばかりですが、日本企業特有の
- 年功序列社会
- 縦社会で上司に意見しづらい
- 転職する事が良く思われにくい
といった文化にさらされていくうちに、ついつい見失ってしまう観点を強く意識できるようになります。
そして本書の内容について触れていく前に、まずは本書のオススメポイントを解説していきます。
ストーリー調で読みやすい
転職の思考法はストーリー形式なため、小説や漫画のような感覚でスラスラ読めます。
そしてこの物語自体に起承転結があり、普通に小説として読んでもおもしろいです。
物語について少し解説すると、転職に悩む主人公こと青野と、コンサルタントの黒岩の話になります。
主人公がコンサルタントと契約して、転職について実生活を通して学んでいくという内容のもの。
正直、現実世界ではコンサルタントと、高額なコンサル料というフレーズほど危険な言葉はありませんが、この主人公は運良く誠実なコンサルに指導を受けれます。
そして転職について学んでいくのですが、その途中で主人公に訪れる人生の転機や、ちょっとしたはプニンが読んでておもしろいです。
- コンサルタントに隠された過去があったり
- 会社の業績が悪化したり
- 主人公の勤務先が、同じコンサルに経営指導を依頼したり
といった、転機が次々と主人公の身に降りかかるため、どんどん次が読みたくなります。
“市場価値”という概念を意識するようになる
転職の思考法では、キャリア形成について合理的に解説しています。
その例として、本書での学びを一部抜粋すると、転職で大切な事は、
- 自分がいる業界の一人あたりの生産性
- 賞味期限切れにならない専門性
- 自分が活躍できる可能性のある環境
といった事があり、これれらの要素をかけ合わせたものが、自分の市場価値 = マーケットバリューだと解説しています。
そのため転職に限らず、より高待遇な条件を得るためには、上記を意識して働く事が大切だと意識するキッカケになります。
好きな事を見つけれる
転職の思考法では、上記のマーケットバリューの軸とは別に、ワクワクする事の軸を持つための方法も教えてくれます。
この本によると、好きなことは見失うものとのこと。
この好きなことを見つける方法は2つあり、
- 他の人から上手と言われるが、自分ではピンとこないもの
- 仕事の中で、全くストレスを感じないこと
から探す、という事です。
詳しい具体例は割愛しますが、参考に私が考えた自分の好きなことを挙げてみます。
私は、仕事の中で全くストレスを感じないこと、から考えてみました。
私がストレスを感じずに打ち込んだ事として、
私は以前プロジェクトを任せられて残業ばかりで苦労しましたが、苦痛ではありませんでした。
この経験から、私は目標を持って自分なりのやり方で挑戦出来る事が好きなんだと気づきました。
このような具体例は本書にもあるため、なにか見つけれる可能性があるためオススメです。
社内だけを見て働く、という概念を認識出来る
本書のストーリー内では、部長が今の地位を維持するために、架空売上を計上していた、という話が出てきます。
この部長の行動は、部長職として居座る事を目的化してしまった結果、間違った行動を取ってしまっていた、という事です。
架空売上の計上は現実離れしてますが、社内だけを見て働く例として、私が思うのは、社内事情にやたら詳しく”社内博士”になっている人です。
本業で成果をだす事に注力するのではなく、社内政治ばかり意識して、自分がいかに良く評価されるか気にしている。
こうした人材は、その会社では評価されるかもしれませんが、マーケットでは評価されないと言えます。
そして本書では、コンサルタント黒岩さんが「マーケットバリューと給料というのは、時間差で一致する」という的を得た事を言っています。
私はこの考えを知ってから、
- 顧客や、会社利益を考えるようにして
- 社内事情に一気一憂しないよう心がけて
- 不必要に社内政治の探索に時間を割かないようにする
ようにしました。
この社内だけを見て働く、という概念は本書で得れる非常に有益なアイデアの一つです。
学ぶべきポイント
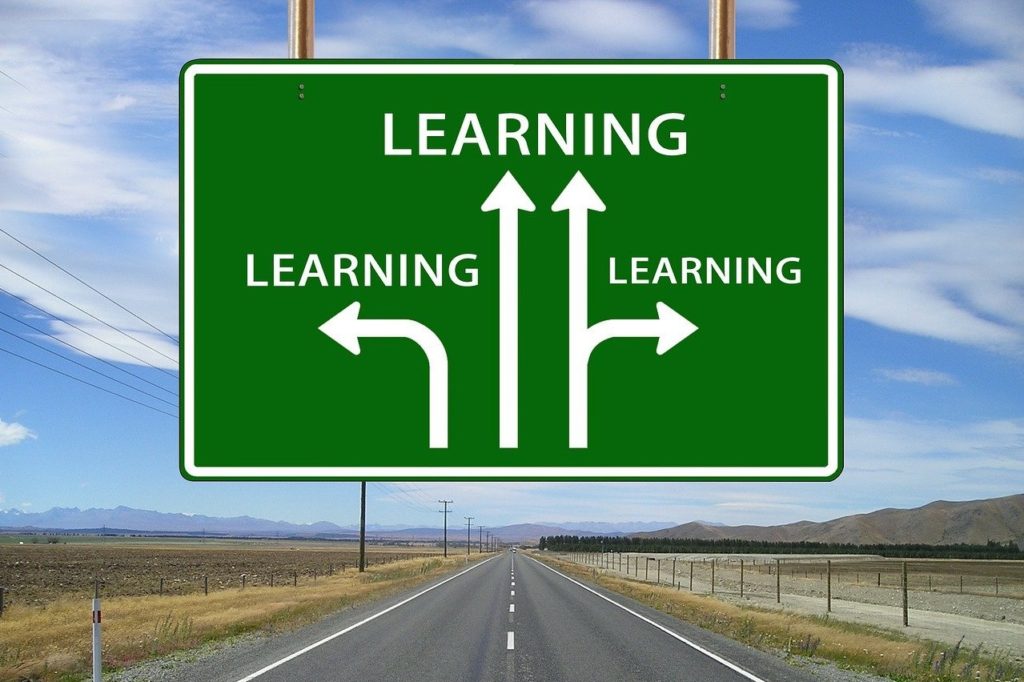
ここからは、本書の特に良かったと感じた部分を一部抜粋して紹介します。
マーケットバリューの概念
本書では仕事での人材の価値を、以下の3種類に分類しています。
- 技術資産
- 人的資産
- 業界の生産性
技術資産は、スキルや経験です。
人的資産とは、人脈で多くの人と繋がりです。
業界の生産性は、業界が成長産業かということです。
そして、この業界の生産性という考え方は盲点の人も多いのではないかと思います。
同じ努力をしても、成長産業と縮小産業では、給与や雰囲気が違う、ということです。
このほかにも、技術資産を更に細かく分解して専門性と経験について、など解説しています。
選択肢を持つ重要性
転職という切り札を持っておく重要性について説明してくれています。
いつでも転職できる選択肢がないと、会社へ依存するしかなくなります。
そうなると会社に利益を出す行動より、会社に残るためにリスクを取らない社員になります。
こうなった社員は、顧客を見ずに上司や上層部などの会社の中を見て働くようになります。
実際にトヨタの社長も、社員に向けた新年の挨拶でこう語っています。
トヨタの看板がなくても、外で戦えるプロを目指して下さい。
私たちマネージメントは、プロになりどこでも闘える力を身につけた皆さんが、それでも働きたいと心から思ってもらえる環境を作り上げていくために、努力してまいります。
トヨタイムズ より
これからは、このように実力主義の社会になっていくため、転職市場で評価される人材になることがリスクを下げる行動になります。
こうした点について、本書では具体的なエピソードをもとに紹介しているのでタメになります。
未来のマーケットバリューを取る
転職をすることで給料が下がるケースについてです。
本書では迷ったら、未来のマーケットバリューが高まる方をとるべきと語っています。
なぜなら今は給与が良くても将来的にマーケットバリューが下がれば、給与も下がる可能性があるからです。
本書では、マーケットバリューと給与は長期で見るといずれ合致すると言っています。
これはつまり、マーケットバリューに対して、給与が高すぎる場合、長期的な目で見るといずれ下がる、逆に給与が低すぎるといずれ上がる、ということです。
この説明だけだとピンと来ないかもしれませんが、本書のエピソードを読みながら学ぶと、もっとイメージ出来ると思います。
やりたいことなんて必要ない
本書では、やりたいことなんて必要ないと語っています。
ほとんどの人にとって、やりたいことよりも、どういう状態でいるかが大切、と説きます。
状態とは、課題や難題が難しすぎない・簡単すぎないか、ということです。
ゲームと一緒で、難しすぎても面白くないし、簡単過ぎても退屈になる、ということです。
そして、ほどよい難易度の状態が維持できれば満足できる人が多いという事です。
これは私の仕事経験からも非常に同感できます。
さらに詳細については本書の中で確認してみてください。
まとめ
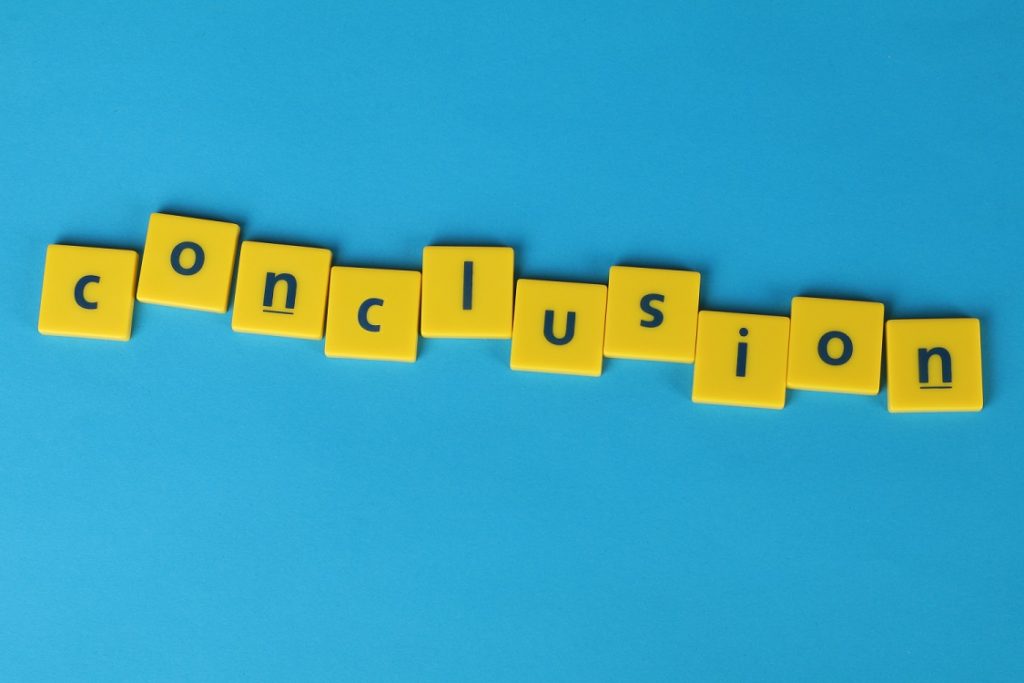
まとめると、転職の思考法では、
- マーケットバリューを考える
- 成長産業の見極め方
- 楽しい仕事について
といった事を語っています。
会社員は全員が読むべきいい本だと思います。
この本は、
- ぼんやりと現状に不安を抱えている
- いまの会社は不満だけどなにが不満かわからない
- 転職を考えているが、なにからしていいか分からない
という人にオススメです。
すごくいい本だったので、おすすめです!
では、また!