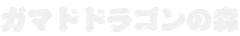- 担当を持ったけど営業の仕方が分からない
- 一人で営業し始めたけど不安が多い
- いきなり営業なんて出来るか心配
この記事は、このような悩みを持つ方向けの発信です。
こんにちは、ガマドドラン(GamadoDragon)です!
初めて営業職で働き出し、入社早々に何も分からないのに担当を持たされて営業活動をさせられと辛いですよね。
そして先輩から、実戦を通して分からない事を聞いてこい、と言われてりしても、
何が分からないか分からず、思い詰めている人もいると思います。
今回はそうした方向けに、意識しておくと営業活動がやりやすくなるノウハウを紹介していきます。
この記事を読むことで、
- これから実践すべき事が明確になる
- 営業活動時の不安が減る
- 得意先の立場に立って考えれるようになる
といったメリットがあります。
営業活動を楽にするノウハウ

知らない事には、後で調べて回答します、でOK
一人で営業をするとなると、不安なのは知らないことを聞かれた時だと思います。
真面目な新入社員ほど、

自社の事や、商品の使い方なんて全て知ってて当然だよな
と考えて、得意先で知らない事を聞かれたら、どうしようと悩みます。
しかしよっぽど頑固おやじか、意地悪でなければ、

申し訳ありません、勉強不足で存じておらず、また帰社後にお調べして、ご連絡させて頂きます。
と言えば、怒る人はいません。
むしろ知ったかぶりをして、自信の無いことをその場で適当に答えて後で間違っていた方が大問題で、これは信頼を失ってしまいます。
そのため困ったら、調べて後で連絡します、と言えばいいと心得ておくと、気が楽になります。
分からない事は質問する
いきなり得意先へ一人で訪問させられると、
- 何を話していいか分からないし
- 顧客の事を知っておかないと失礼だし
- 業界や、商品の現場の使い方は知ってて当然だし
と感じて、自分ばかり話すのも気が引けるし、かといって質問する内容も考え過ぎてしまい、うまく話せなくなってしまいます。
しかし普通の会社員であれば、新人営業マンが自社の事を全て知ってなくても当然と感じるので、
- 得意先の主力サービスの販売先を聞く
- 商品を使用する現場の状況を聞く
- 競合他社品の使用状況を聞く
といった事をしても、「失礼だなお前」と言われるような事は滅多にありません。
そのため会話の中で初見の単語が出たり、得意先の販売先の話になったら、思い切って質問する事で得意先への理解が深まっていきます。
さらに前任者から引き継いだ情報も変わっていくため、自分が質問することで、実は引き継いだ情報と違っていたという事も起きます。
むしろ得意先の現状を教えてもらう事により、
- 競合他社の価格情報を仕入れたり
- 顧客の困っている事を知ったり
- 業界でのトレンドを知れたり
して、これらの情報を参考に商品提案が出来たり、自社品の開発に役立てる事もできます。
そのため得意先の情報を得てくる事も営業の仕事だといえます。
質問するときの注意点として、
- 同じことを聞かないように聞いた事はメモする
- 使ってもらってる自社品ぐらいは知っておく
ぐらいは意識しておくと良いです。
常にメモをする
質問の注意点で上述しましたが、メモは便利で大切です。
客先でメモを取るようにする事で、
- 同じ質問をする失態を防げる
- 真面目な印象がつく
- 会話に詰まった時に、メモするフリして話題を探せる
といったメリットがあるため、メモを取ってない人は、特に理由がないなら取るようにした方が良いです。
また話が長引いた時など、会話の前半に話した議題や自分のすべき事を忘れがちですが、こうした事もメモしておくことで防げます。
なおメモ帳の懸念点として、年月が立つと膨大な紙の量になり持ち歩けなくなる事です。
そのため私の取っている工夫としては、客先ではメモ帳にメモして、後でGoogle Calendarのメモに要点を箇条書きしています。
こうする事で、
- スマホひとつで、どこでもメモを見れる
- 検索機能があるので、すぐ調べられる
- 前回会った日付も分かる
といったメリットがあります。
さらに詳しい使い方については下記記事で解説しています。
最初のうちは頻繁に訪問する
私の経験上では、
最初に高頻度で訪問して、自分の存在を認知してもらってから訪問頻度を下げる方が、
定期的に同じ頻度で訪問するより効率が良く楽だと思っています。
その理由として、最初に高頻度で顔を出した方が覚えてもらいやすい事と、覚えてもらったら次の訪問も気楽になるからです。
具体的な例を出すと、
- 1年に1回しか来ない人より
- 初年度で2回来て、後は2年に1回来る人
の方が、相手の記憶に残ります。
そして一度顔を覚えてもらえれば、次回からの訪問も、「ああ〇〇さんね、どうぞどうぞ」となって訪問しやすくなります。
用がなくても訪問して良い
恐らく営業を始めた人の多くが抱くであろう

用事のない客に行く必要なくね?向こうの時間も取るし迷惑でしょ。営業の存在価値あんの?
という感覚 。
しかし用がなくても訪問するからこそ、
- 相手が用事を思い出したり
- 他社に問い合わせようとしてた事を、こちらに聞いてくれたり
- 存在を思い出して、今後も問い合わせしてくれたり
するようになります。
特に得意先の担当者が新しい人になった場合、
仕入先を知らないので、とりあえずよく来る業者に問い合わせるという事が起こるため、訪問するのはやはり大切です。

とはいえ時間取られるのって迷惑じゃない?家に新聞の勧誘来るとウザいって感じるし。
と感じる人もいると思いますが、
プライベートと仕事では感覚が違うもので、
仕事中に取引先が来社する事は違和感がないため、取引先が来社する事を迷惑と思う人は少ないです。
営業フレーズは、挨拶、で充分

用事が無くて客先に行くとしても、なんて言って行くのか分からないんだけど
と感じる人は、とりあえず「挨拶でお伺いしたい」と言っておけば問題ありません。
その他には状況によっては、
- 近くに来たので挨拶で
- 明日近くを通るので挨拶で伺っても良いですか?
- しばらくお伺い出来てないので、来週伺っても良いですか?
などと組み合わせて言えば、不自然さが無くなり邪険にされにくいです。
もちろんこうした理由のない訪問に対して、時には、

大した用事がないなら来ないでくれ
と言ってくる人もいますが、こうした得意先へは、
- 別の担当者の人に訪問する
- メールや電話だけでも繋がっておく
- 年末年始などのイベントを活用して連絡する
といった方法で定期的にコンタクトし続けてみると良いです。
優先順位をつけて訪問する
真面目に営業活動に取り組んでいると、行く会社が多過ぎて時間不足になってきます。
その結果、結局どの会社への営業も中途半端で認知されないという状況になる可能性があります。
この事態を避けるために、得意先に優先順位をつけて必ず訪問すべき会社と、そうでない会社に分類します。
そして優先順位が高い会社へは3ヶ月に1回は連絡するか、訪問する、といったルールを決めて、そうでない会社は年に1回は顔をだす、などと決めておきます。
こうする事で大切な顧客との関係を早く築けます。
ちなみにこの優先順位の付け方ですが、私は下記を基準としています。
- 得意先の規模の大きさ
- 過去数年の売上・利益金額の高さ
- 得意先内においての自社品の使用率の高さ
加えて面会する人にも優先度を決めて、キーパーソンに会うようにするのも大切です。
このキーパーソン選定は、肩書きや役職だけではなく、得意先内の人間関係を観察する必要があるので難しいところです。
最後に:外回り営業は慣れてしまえば楽

外回り営業は、良くも悪くも自由です。
そのため出先で困っても助けてくれる人がおらず、始めのうちは自力で以下の事を乗り越えないといけないのでしんどいです。
- 客先の顔と名前を覚えていく
- 使ってもらってる自社品を覚える
- 話す話題を考える
- 客先の場所を覚える
しかし次第にこれらに慣れてくると、
- 最初に話すフレーズが定まってくる
- 客先と顔見知りになり、気軽に訪問できるようになる
- 客先と情報交換して、別の客先でも話せる話題がさらに増える
- 客先を辞めた人が、同業界の会社に転職してネットワークが広がる
と、どんどん好循環のサイクルに入り、自分でたいていの問題を解決出来るようになると、営業時のストレスも減り、外回りが快適で自由な時間になっていきます。
さらに出張が多い部門だと、出張先が担当になれば、さらに自由度が増してやりたい放題なので、頑張る価値はあります。
ちなみに後々楽出来る職場の特徴をまとめた記事も記載しておきます。
もし営業を1年程度続けてみて、全然無理そうだと感じる人は営業以外の道を模索するのも良いと思います。
今は辛い状況かもしれませんが、行動し続ければいずれ自分の目指す環境にたどり着けます。
そのためあまり悲観的にならずに頑張り続けましょう!
それでは、また!
※関連記事